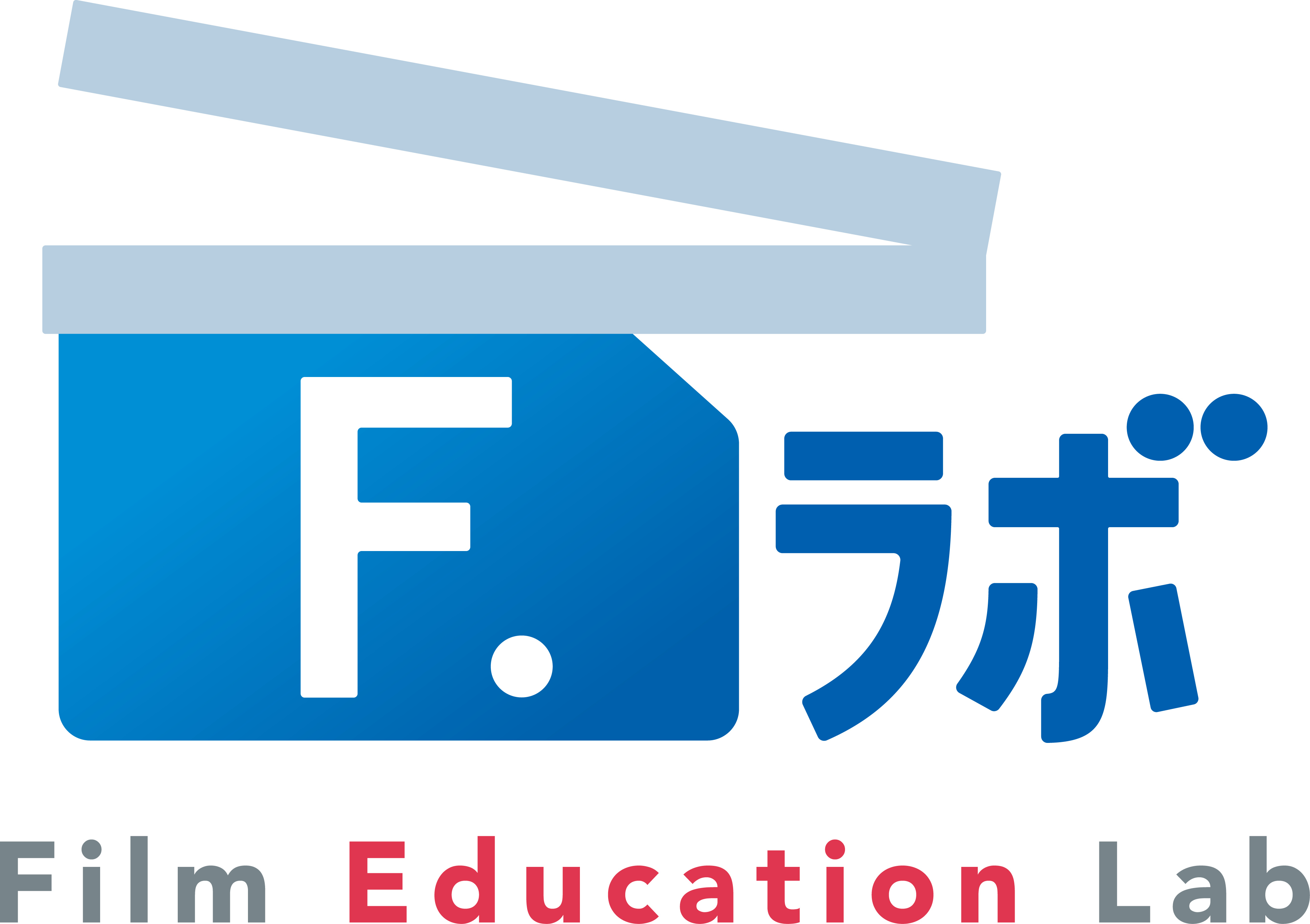
発表のために動画制作を授業で取り入れてみたけれど、今ひとつ学びが深まらない……。そんな経験はありませんか?
本来、映像制作の過程には学びがたくさんあります。
協働的に学びあい、試行錯誤しながら作品を高め、表現を振り返る。この一連の学びのプロセスを、映像のプロであり教育者でもある山﨑カントクがメソッド化したのが、F.ラボのプログラム<Film Education>です。
単に動画をつくって楽しい、で終わらせない。
映像制作を活用した授業を通して、子どもたちの学びを一歩前へ進めてみませんか?
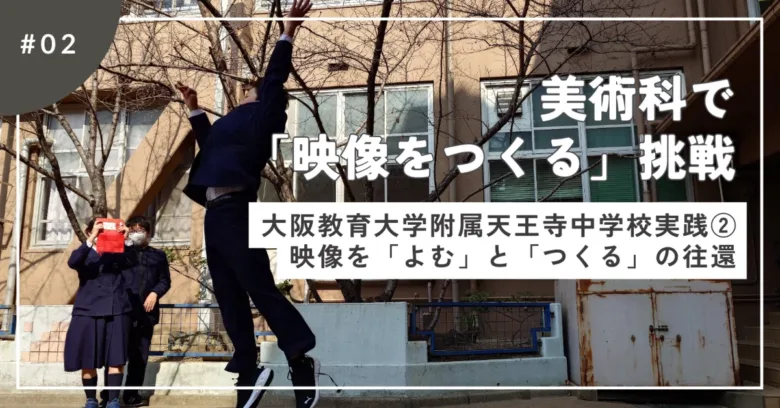
2025.8.23
美術科で「映像をつくる」挑戦
前回の記事では、国語科の伊藤博紀先生が担当された「映像をよむ」授業の様子をレポートしました。新海誠監督のアニメーション作品を題材に、構図の決め方や光の影の加減、編集の切り取り方など、言葉以外の「非言語表現」にも目を向けな […]
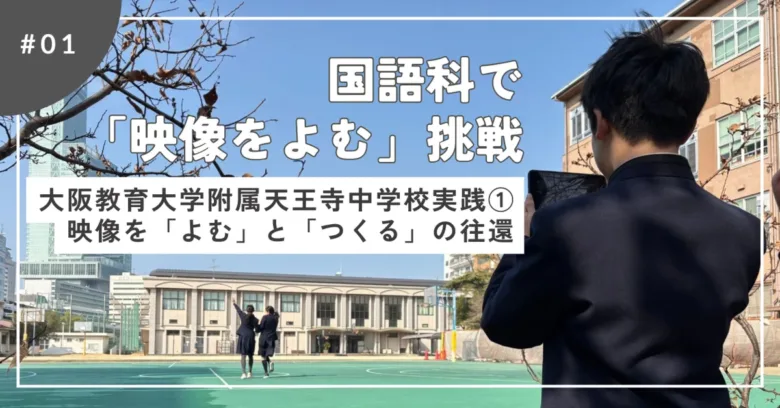
2025.8.20
国語科で「映像をよむ」挑戦
F.ラボは、2025年2月、大阪教育大学附属天王寺中学校にて、授業プログラムを実施しました。今回の授業プログラムには、ひとつ大きな特徴があります。それは、国語科で「映像をよむ」授業と、美術科で「映像をつくる」授業を組み合 […]

2025.8.14
美術科から広がる映像表現の可能性
映像表現を自ら体験することを通して、未来を生き抜く力を育む授業プログラムを提供しているF.ラボ。なかでも人気のプログラムが非言語だけで映像表現に挑戦する「エモい映像をつくろう」です。「どうすれば相手に伝わるのか」を問いな […]
F.ラボの大きな特徴は、決まったプログラムを行うのではなく、オーダーメイドで学びを設計するところです。1クラス単位でも、学年でも、全校でも対応可能。私立・公立問わず、小中高大や特別支援学級の他、フリースクールや塾など30以上の教育機関と連携して、60以上の授業プログラムを実施中です。
1回完結型の出張授業から中長期的に伴走をする探究型プログラムまで様々なプログラムを用意しており、それらをベースに各学校・学級の実態に合わせて調整をします。
「総合的な学習(探究)の時間のアウトプットに使いたい」「学年の振り返りのために映像を制作したい」「美術科の『表現』の単元で活用したい」など先生の「こんなことやりたい!」を気軽にご相談ください。
ドルトン東京学園中等部・高等部
ぐんま国際アカデミー高等部
東京都立両国高等学校
静岡県立掛川高等学校
神奈川県立横浜清陵高等学校
神奈川県立秦野高等学校
北鎌倉女子学園中学校
鎌倉市立玉縄中学校
鎌倉市立深沢中学校
鎌倉市立大船中学校
鎌倉市立岩瀬中学校
鎌倉市立手広中学校
世田谷区立世田谷中学校
練馬区立光が丘第三中学校
横浜市立緑園西小学校
鎌倉市立小坂小学校
柏市立逆井小学校
船橋市立金杉台小学校
実践女子大学
実践女子大学短期大学
山野美容芸術短期大学
探究学舎
OZ Field
TMS 東京映画映像学校
他

F.ラボの代表・山﨑達璽は、プロの映画監督・映像ディレクターでありつつ、映像制作を通じた教育を20年以上にわたって続けています。また、山﨑に共鳴した教育の実践家や現役公立小中学校の先生方がアンバサダーやアドバイザーとして参画しています。F.ラボのプログラムは、映像制作の専門家と学校教育の専門家集団とが作り上げた、現場叩き上げのメソッドなのです。
メンバー紹介